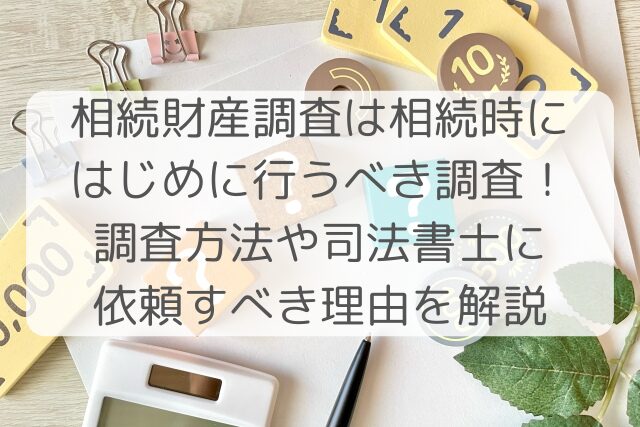世界の相続制度を比較!|日本・米国・中国・UAEの違いと文化背景

相続は現在生きている人、誰にとっても避けられないテーマですが、相続の仕組みは国によって大きく異なります。
各国の相続の制度には文化や歴史、宗教の違いが反映されており、背景を知ることがトラブル予防につながるでしょう。
今回は、日本・アメリカ・中国・UAEの4つの国を取り上げ、それぞれの相続制度の特徴と、その背景にある考え方を比較して紹介します。
なぜ国によって相続制度が違うのか?
国によって相続制度が異なるのは、単に法律が異なるからというわけではありません。
制度の背景には、それぞれの社会が育んできた価値観が深く影響しています。
1−1.相続制度は「文化・宗教・歴史」の鏡
相続制度は、単なる法律のルールではなく、各国の価値観を反映した社会の仕組みです。たとえば、日本では子どもが親の財産を引き継ぐことが一般的ですが、中国では、親も子どもと同列に相続人となります。
これは「親が子を支える」か、「子が親を支える」かという文化の違いに基づくものです。また、イスラム諸国のように、宗教が法制度に深く関与している場合、信仰に基づく分配ルールが厳格に定められています。
このように、相続制度には家族観や宗教的価値観、歴史的背景が色濃く反映されており、国によって大きく異なるのは当然ともいえます。
1−2.国際化が進む今こそ「違い」を知る必要がある
日本国内でも、国際結婚や外国人の不動産所有が増加しています。令和6年時点で、外国人の在留者数は376万人を超え、総人口の約3%に達しました。
こうした現実を踏まえると、日本の法律だけを基準に相続を考えるのは不十分といえるでしょう。
異なる国籍同士での相続や、海外の財産を含むケースでは、それぞれの国の制度が関わってくるため、制度の違いを正しく理解しておくことが、将来の相続トラブルを未然に防ぐ鍵となります。
2.日本の相続制度の基本とその背景

日本では、民法によって相続のルールが定められています。
特徴的なのは、常に配偶者が相続人となる点です。
2−1.配偶者と法定相続人|法定相続分
常に相続人となる配偶者と一緒に相続するのは、以下の順序で定められた法定相続人です。
- 第1順位:子(実子・養子含む)
- 第2順位:直系尊属(親・祖父母)
- 第3順位:兄弟姉妹
相続分の割合は、相続人の組み合わせによって変わります。
- 配偶者+子:配偶者1/2、子で1/2を等分
- 配偶者+親:配偶者2/3、親で1/3を等分
- 配偶者+兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟姉妹で1/4を等分
配偶者がすでに亡くなっている場合は、相続順位に沿って相続権が移り、相続人が変わります。
例えば、母が亡くなった場合、先に父(母の配偶者)が亡くなっていれば、相続人は母の子どもとなります。
2−2.日本の相続制度の背景
日本では、配偶者が比較的厚く保護されている仕組みとなっています。
この背景には、戦後に「家制度」が廃止され、核家族化が進んだことが関係しています。かつては、「家督相続」という仕組みのもと、長男が家と財産を引き継ぎ、家全体を守るという考え方が主流でした。
しかし現代では、夫婦それぞれの生活を保障することが重視され、特に配偶者に手厚く分配されるような制度設計となっています。
2−3.戸籍制度|特殊性のある日本の仕組み
日本の相続実務に欠かせない「戸籍謄本」ですが、世界基準でみると特殊性のある制度です。
戸籍をたどれば、被相続人の親子関係や兄弟姉妹、さらに甥姪まで把握することができます。そのため、相続人を確定する際には戸籍の収集が不可欠です。
しかし、「家族単位で全員の関係を一元的に登録する仕組み」は極めて珍しく、現代では日本と台湾などでしか採用されていません。
例として、韓国もかつては戸籍制度がありましたが、2008年に家族関係登録簿制度へ移行し、個人単位での登録へ改められています。
3.アメリカの相続制度|夫婦は共同で財産を築くという考え方
アメリカでは、州ごとに相続制度が異なるため一律ではありませんが、アリゾナ州やカリフォルニア州などの一部の州(9州)では「共同財産制(コミュニティ・プロパティ/Community Property)」という制度が採用されています。
3−1.共同財産と個人財産の仕組み
一部の州で採用されている「共同財産制」の特徴は、結婚後に夫婦が築いた財産を「共同のもの」として扱う点にあります。
たとえば、夫が亡くなった場合、共同財産のうちの「夫の持分1/2」は相続対象となりますが、基本的には残りの1/2はもともと妻のものとされます。残りの夫の持分1/2についてのみ相続があるため、結果として妻が共同財産全体を引き継ぐケースも珍しくありません。一方で、結婚前に持っていた財産や、相続や贈与で得た財産は「個人財産(セパレート・プロパティ/separate property)」として区別されます。被相続人の個人財産は、法定相続人と法定割合で分けることになります。
3−2.アメリカの夫婦観と歴史的背景
アメリカのこのような制度の背景には、「夫婦は対等なパートナーであり、共同で財産を築く」というアメリカ独自の夫婦観があります。
共同財産制はすべての州では採用されているわけではありませんが、アメリカ全土で夫婦共同名義の口座(ジョイントアカウント)を持つことは一般的です。また、夫婦が契約を交わすことで共同財産制を選択できるオプトイン制度もアラスカ州、フロリダ州などの一部の州で導入されています。こうした慣習からも、夫婦で財産を共有する意識が広く浸透していることが分かります。
西部開拓時代に、夫婦が協力しながら荒野を切り開いてきた歴史もあり、「夫婦共同」の思想が制度に深く根づいているといえるでしょう。
4.中国の相続制度|親も子も“第1順位”で相続人
中国では、配偶者・子・父母がすべて「第1順位」の相続人とされ、基本的には平等に分け合うルールとなっています。
4−1.相続順位と分配ルール
中国では、同順位の相続人の相続割合は原則同じです。
たとえば、配偶者・子ども2人・父母の5人がいる場合、「それぞれが1/5ずつを相続する」というのが基本です。
|
第1順位 |
配偶者・子・父母 |
|
第2順位 |
兄弟姉妹・父方の祖父母・母方の祖父母 |
日本の感覚では、子がいれば親は相続しない(直系尊属は第2順位)という認識ですが、中国ではそうではありません。
4−2.「孝」に根ざした家族観
中国では、「親を大切にする」「親が子どもを支えるのは当然」という価値観ではなく、「子どもが親を支える」という「孝」の思想が根づいています。
また、実際に被相続人の介護や生活の支援などに大きく関与した相続人については、他の相続人と比べて多く分けることもできるという調整規定もあります。これは、日本の「寄与分」と似た仕組みですが、中国ではより柔軟に運用されているようです。
UAE(アラブ首長国連邦)の相続制度|宗教が強く影響するイスラム法
UAE(アラブ首長国連邦)では、相続は「イスラム法(シャリーア)」に基づいて行われます。
イスラム法とは、イスラム教の教えに基づいた法律体系で、信仰や生活全般のルールを定めたものです。
5−1.イスラム法に基づく分配ルール
イスラム法の大きな特徴は、「男女によって相続分が異なる」という点です。
たとえば、夫が亡くなり、妻と息子・娘がいる場合:
- 妻は1/8
- 残りの87.5%を息子と娘が「2:1」の割合で分ける(=息子が2/3、娘が1/3)
日本人の感覚からすると「不公平」と感じるかもしれませんが、イスラム社会では「男性が家族を養う責任を持つ」という考えが制度の前提となっており、これは合理的とされています。
5−2.相続時の適用法と回避する手段
UAEでは、外国人であってもイスラム法が適用されることがあります。
とくに不動産などの財産がUAE国内にある場合、何も対策をしていないとイスラム法に基づく分割になるおそれがあるため、現地では外国人向けの遺言登録制度が整備されています。
遺言を残すことで、イスラム法による割合でなく、希望した割合で相続人へ財産を残すことができるようになります。
国際相続でカギになる「準拠法」の考え方
国際相続では、「どの国の法律が適用されるのか?」という視点がとても重要です。これを「準拠法(じゅんきょほう)」と呼びます。
基本的には、以下のルールに基づいて判断されます。
- 動産(預金・株式など):被相続人の国籍に基づく法律が適用
- 不動産:不動産がある国の法律が適用
日本では、法の適用に関する通則法(通称:通則法)があり、第36条において「相続は、被相続人の本国法による」と規定されています。
つまり、日本に住んでいる外国籍の方が亡くなった場合、原則としてその方の国籍の法律が相続に適用されますが、日本国内の不動産については日本の法律が適用されることになります。
このように、複数の国の法律が関わるため、適切な対応をしていないと意図しない相続分配がなされてしまうリスクが高くなってしまいます。
※なお、反致(通則法第41条に規定)により、日本国籍でない場合も日本法が適用される場合があります。
まとめ|相続の違いを知ることが、トラブル予防の第一歩
相続制度は、単なる法的ルールではなく、その国が大切にしてきた「文化」「家族観」「宗教観」そのものが映し出されたものです。
国際結婚や外国に籍がある人との財産共有が身近になっている今、「日本の常識が通じないこと」を前提として考える必要があります。
特に不動産や金融資産を複数の国にまたいで保有している場合、遺言書を作成する、準拠法を意識するといった対策は欠かせません。
将来的なトラブルを避けるためにも、早めに国際相続(渉外)分野に精通した専門家へ相談することをおすすめします。
拓実リーガル司法書士法人ではこれまでにも国際相続のお手続きをお引き受けしています。お気軽にご相談ください。