昔の戸籍ってこんなに奥深い【相続手続きこぼれ話】
相続手続きで出会う「戸籍の歴史資料」
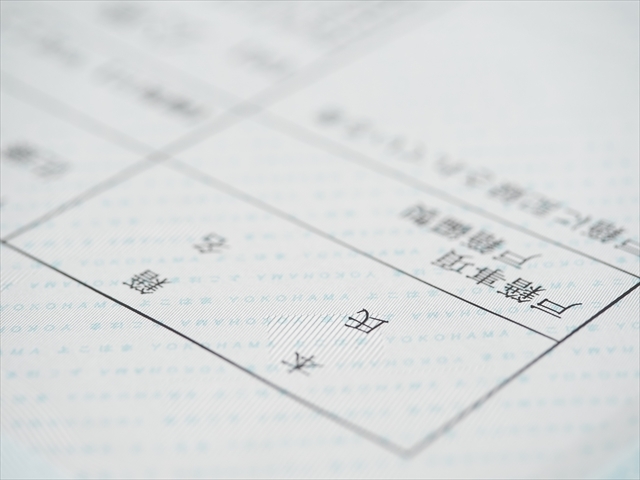
「戸籍」と聞くと、堅くて難しそうな印象を持つ方もいらっしゃるかもしれません。 しかし、実際に相続手続きで古い戸籍を収集していくと、そこには家族の歴史や日本の時代背景が色濃く反映されており、単なる証明書を超えた“人生の記録”としての側面が見えてきます。
本記事では、司法書士としての実務経験を踏まえ、昔の戸籍に見られる特徴や注意点について、ご紹介いたします。
昔の戸籍には、現代では見られない記録が残されている
相続登記や法定相続情報一覧図の作成には、被相続人の「出生から死亡までの戸籍」の取得が必要です。
この過程で、昭和初期や大正、明治時代に作成された「改製原戸籍」や「除籍謄本」にたどり着くことがあり、それらには現行の制度とは異なる形式や記載方法が見られます。
戸籍が“家”単位だった時代
昭和32年以前の戸籍は、「戸主(こしゅ)」を中心とした“家”が基本単位でした。 家族全員が1つの戸籍にまとめられており、「戸主の妻」「長男」「養子」などの記載が並んでいます。
家制度を反映したこの仕組みは、現代の「夫婦+未成年の子」という構成とは異なり、戸主の交代や分家の記録など、当時の家族のあり方を知る手がかりになります。
壬申戸籍に見られる情報と、現在の戸籍との違い

明治5年に作成された「壬申戸籍(じんしんこせき)」には、職業、身分、家系、出身地などが非常に詳細に記載されていました。 たとえば「士族」「農業」「部落」などの表現が含まれていたとされています。
しかし、壬申戸籍は現在では完全に非公開とされており、閲覧や謄本の交付は一切認められていません。 そのため、相続手続きにおいてこれらの戸籍を用いることはできません。
なお、現在取得できる改製原戸籍や除籍謄本では、職業や身分に関する記載は原則存在せず、差別的表現も既に除かれています。
平成改製と戸籍のコンピュータ化
昭和改製に加え、平成6年には戸籍のコンピュータ化(いわゆる平成改製)が実施されました。 これにより、戸籍の様式が大きく整理され、旧来の手書き様式から電算化された形式へと移行しています。
この改製により、旧戸籍の内容は新しい戸籍には引き継がれず、必要な情報を確認するためには改製前の戸籍(改製原戸籍)を取得する必要があります。 なお、平成改製時に電算化される前の戸籍も「改製原戸籍」として交付されるため、改製原戸籍には昭和改製・平成改製の両方の前段階の戸籍が存在し得ます。
「樺太」「台湾」など、かつての日本の地域が登場することも
戸籍をさかのぼっていく中で、「樺太豊原町」「台湾台北市」など、現在の日本地図には存在しない地域が本籍地として登場することがあります。
これは、かつて日本が統治していた旧外地(南樺太・台湾・朝鮮など)に関係しています。
統治下にあった旧外地の戸籍
明治から昭和20年の終戦まで、日本の戸籍制度は南樺太や台湾にも適用されていました。 そのため、当時これらの地域に本籍があった方の戸籍には、次のような記録が見られます。
- 大正12年 樺太豊原町にて出生
- 昭和21年 東京都中野区へ転籍
このような記載からは、戦後の引き揚げや転籍の経緯がうかがえます。
樺太の戸籍は今でも取得できる?
結論からいえば、条件を満たせば取得可能な場合があります。
戦後、南樺太の戸籍は、一部が日本本土の役所に移管され、北海道内の市町村や法務局に保管されています。
ただし取得には、
- 保存期間(除籍後150年)内であること
- 転籍先が明確であること
- 正当な請求理由(例:相続)があること
といった条件を満たす必要があります。
また、保管自治体が特殊な場合もあるため、個人でたどるには難しいこともあります。 もし被相続人の戸籍のなかで樺太の記載を見つけたら、もしくは樺太にいたことが分かっている場合は、専門家に相談しながら、戸籍収集を進めるとよいでしょう。
戸籍には家族の歴史が詰まっている
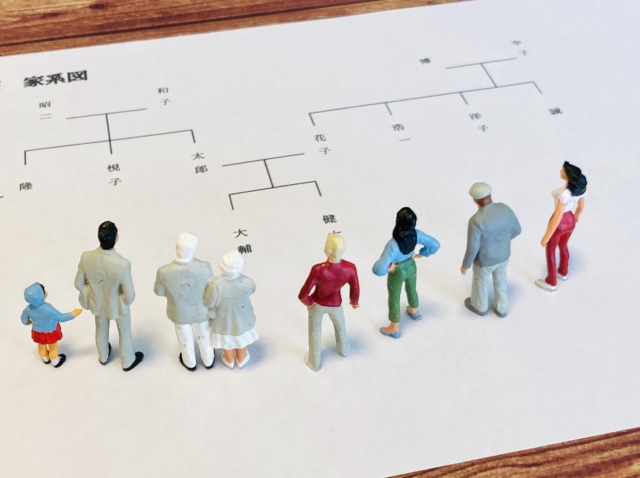
戦時中ならではの記載が残ることも
昭和10年代から終戦前後に作成された戸籍には、戦時体制下ならではの記録が残っていることがあります。
たとえば以下のような内容が記載されている場合があります。
- 男性の「現役兵」「応召」「除隊」「戦病死」など兵役に関する記録
- 疎開や戦火を避けた転籍の履歴
- 本籍地が朝鮮・台湾・旧満州(中国東北部)である記録
- 「死亡地:旧満州国哈爾浜市」など、戦地での死亡・不在の記録
これらは現在でも改製原戸籍や除籍謄本に記載されていることがあり、相続人の知らなかった事実や、戦争と家族の関わりが見えてくるケースもあります。
社会背景を映す記録としての戸籍
現在交付される戸籍(改製原戸籍・除籍謄本)には、「庶子」「士族」などの表現は原則として既に記載されていないか、交付時点で除かれています。 これは差別的な取扱いを防ぐため、法務省の運用上配慮されているものです。
戸籍を通して、家族の歴史のみならず日本の社会制度の変遷を知ることができるのは、相続という機会ならではといえます。
相続手続きの中で戸籍が語ること
司法書士として相続登記や遺産分割協議のお手伝いをする中で、戸籍の記録からご家族の移動や人間関係の変遷が見えてくることがあります。
- 知らなかった養子縁組の記録
- 遠方にいた兄弟姉妹の存在
- 本籍の移動が示す引き揚げの歴史 など
相続は“財産の手続き”であると同時に、“家族の記録をたどる行為”でもあるのです。
戸籍制度の主な歴史の流れ
|
時代 |
概要 |
|
明治5年 |
「壬申戸籍」作成。身分や職業の詳細が記載されたが、現在は完全非公開。 |
|
昭和32年 |
戸籍様式が大きく改正(縦書き・家単位)。この戸籍が「改製原戸籍」となる。 |
|
平成6年 |
戸籍のコンピュータ化(平成改製)。電算処理された形式に変更。旧様式は「改製原戸籍」として保存。 |
|
令和7年(予定) |
氏名のカタカナ読み仮名の記載が開始(2025年5月26日施行)。 |
まとめ:戸籍は過去と今をつなぐ大切な記録
相続手続きに必要な戸籍には、現代の制度では見られない多くの情報が記録されています。 それは法律文書でありながら、家族の軌跡や日本の歴史を映し出す貴重な記録でもあります。かつての暮らしや家族のつながり、戦争や社会制度の変遷まで、戸籍を通して見えてくる“物語”は、財産を受け継ぐ以上に心に残ることも少なくありません。
戸籍を収集することは、単なる作業ではなく、過去と今をつなぐ大切なプロセスです。しかし実際には、「どこまで取ればいいのか分からない」「昔の戸籍が読めない」など、相続人の方が戸籍の扱いに戸惑うケースも多く見受けられます。そうしたお困りごとも、相続に精通した専門家である司法書士であれば、的確にサポートし、スムーズに解決へと導くことが可能です。
相続を通して戸籍をひもとくことは、家族の歴史や自分自身のルーツを見つめ直す機会にもなります。書類の背後にある背景を丁寧に読み解いていくことで、単なる手続き以上の意味を感じられるはずです。
戸籍収集や相続登記でお困りではありませんか?
拓実リーガル司法書士法人では、豊富な経験と実績を活かして丁寧にサポートいたします。
- 複雑な戸籍の読み解き
- 戸籍収集の代行
- 相続登記のワンストップ対応 など
まずはお気軽にご相談ください。 お一人おひとりのご家族に寄り添いながら、最善のご提案をいたします。
📞 ご相談窓口:https://www.t-legal.net/contact/
📍 対応エリア:立川・新宿を中心に東京都全域(全国対応も可能です)
初回相談は無料です。メールや電話、お問い合わせフォームからご連絡くださいませ。


